
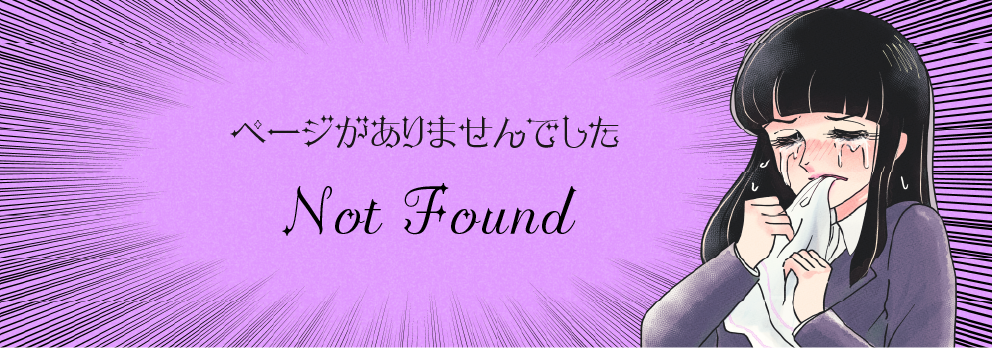
人気の検索
数学の検索
色の検索
漢字の検索
国語辞典の検索
Function commands
| Command | Description | Examples |
|---|---|---|
| frac | 分数にする | frac 1.2 |
| gcd | 最大公約数 | gcd 4 6 |
| lcm | 最小公倍数 | lcm 8 12 |
| ceil | 小数切り上げ | ceil 5.7 |
| floor | 小数切り捨て | floor 3.1 |
| rint | 一番近い整数 | rint 9.6 |
| sqrt | 平方根 | sqrt 16 |
| expand | 式の展開 |
expand (3*x+1)*(x-5)**2
|
| factor | 因数分解 |
factor 3*x**2-5*x-4
|
| e | e のべき乗 | e 2 |
| log | log の値 | log 7 |
| erf | エラー関数 | erf 0.1 |
| gamma | ガンマ関数 | gamma 0.8 |
| log10 | log10 の値 | log10 100 |
| log2 | log2 の値 | log2 8.0 |
| log1p | log1p の値 | log1p 4 |
| isqrt | isqrt の値 | isqrt 15 |
Function commands
| Command | Description | Examples |
|---|---|---|
| cos | cos の値 | cos 6.2 |
| sin | sin の値 | sin 2 |
| tan | tan の値 | tan 45d |
| acos | cos の逆関数 | acos -0.3 |
| asin | sin の逆関数 | asin 0.5 |
| atan | tan の逆関数 | atan 6 |
| cosh | Hyperbolic cos | cosh 2.1 |
| sinh | Hyperbolic sin | sinh 0.4 |
| tanh | Hyperbolic tan | tanh -1.9 |
| acosh | cosh の逆 | acosh 2.7 |
| asinh | sinh の逆 | asinh -1.6 |
| atanh | tanh の逆 | atanh 0.3 |